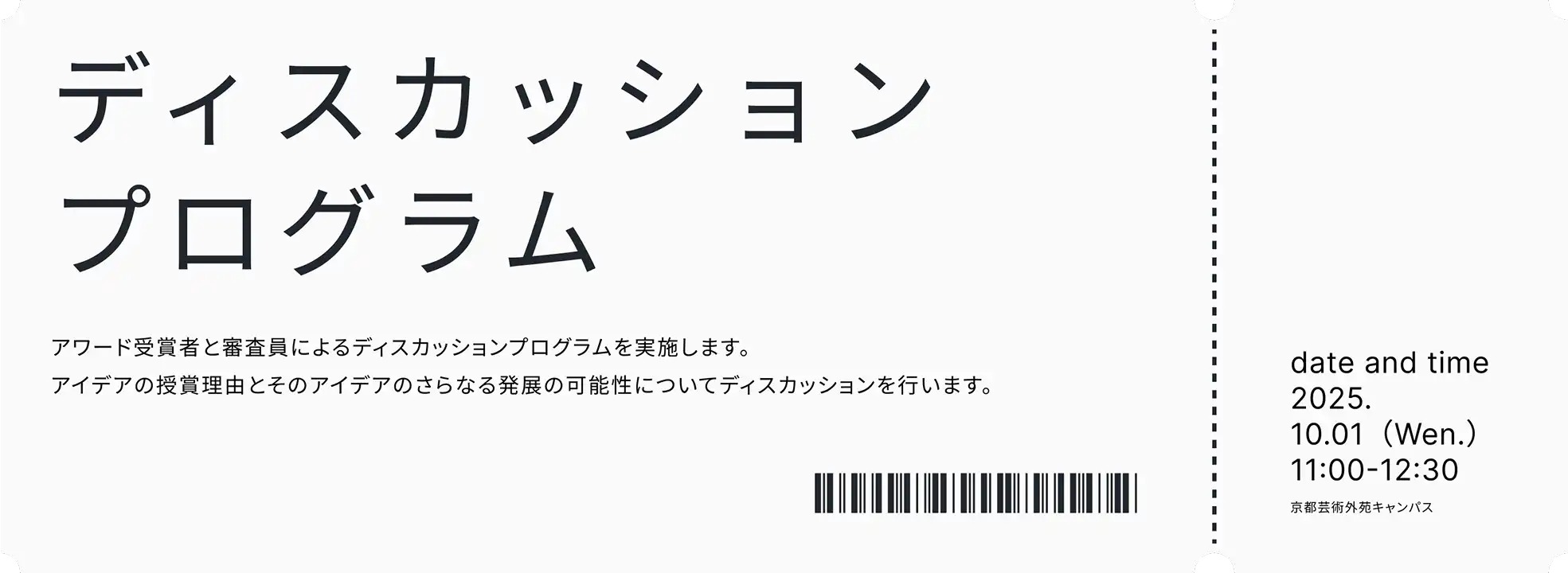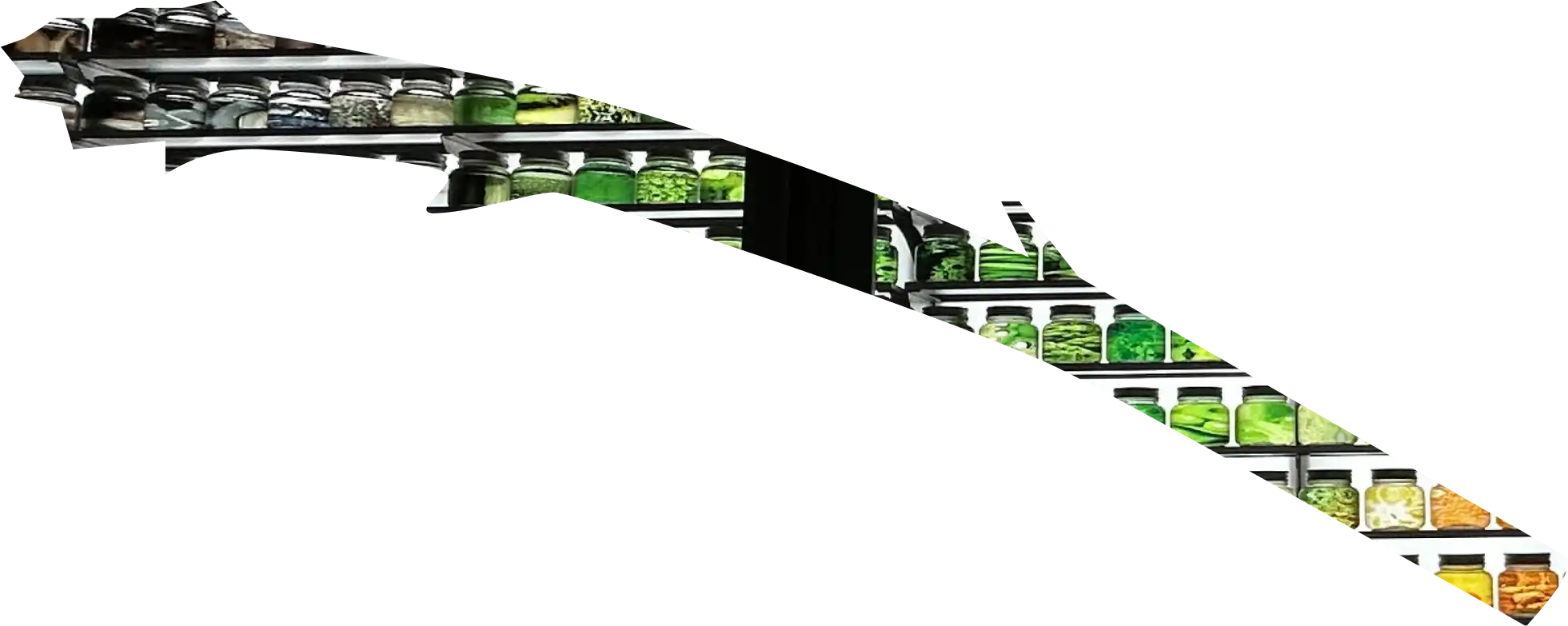万博
特別講義
アワード
SCROLL DOWN



京都芸術大学食文化デザインコースでは、
サプライヤーとして協賛している
2025年大阪・関西万博の
シグネチャーパビリオン「いのちをつむぐ」を
テーマとする
「EARTH MART」を貴重な食の学びの場と捉え、
万博の特別講義プログラムを2025年度に
実施しました。
これまでの万博特別講義で得た学びから、
その締めくくりとしてアワードを実施しました。
募集内容
Call for submissions
応募テーマ
EARTH MARTを通して考える
「食のミュージアム」アイデア募集
EARTH MARTをきっかけに、日本のどこかに「食のミュージアム」をつくるとしたら、どのようなものがよいと思いますか?食といのちの当たり前をリセットし、ワクワクする食の未来を創るミュージアムのアイデアを考えてください。
条件:下記の要項のいずれかを含むアイデアとします
・生産者への応援、励みにつながる
・食を通して、その土地への興味関心・愛着につながる
・ガストロノミーツーリズムにつながる
審査の視点
・共感性/納得性
・ストーリー性/デザイン性
・実現性
・熱意(パッション)
審査員
一次審査
食文化デザインコース専任教員
二次審査
小山 薫堂
放送作家/大阪・関西万博テーマ事業「EARTH MART」プロデューサー/京都芸術大学副学長・食文化デザインコース監修/オレンジ・アンド・パートナーズ代表/下鴨茶寮 主人/「RED U-35」総合プロデューサー

佐藤 洋一郎
農学博士(専攻:遺伝子学)/ふじのくに地球環境史ミュージアム 館長/京都芸術大学食文化デザインコース「日本の食らしさとは」講義担当/和食文化学会初代会長/「和食展」監修

石川 伸一
農学博士(専門:分子調理学)/宮城大学食産業学群教授/大阪・関西万博「EARTH MART」アドバイザー/京都芸術大学食文化デザインコース「おいしさの科学」「食の未来ビジョン」講義担当/近著に『Cook to the Future』など

大屋 洋子
食ビジネスプロデューサー/大阪・関西万博「EARTH MART」企画運営ならびに「EARTH FOODS 25」検討委員オーガナイザー/京都芸術大学食文化デザインコース企画・運営リーダー/オレンジ・アンド・パートナーズ食ビジネス部門長

アワードの設定について
本アワードでは、優劣やランキングによる賞は設けず、食文化デザインコースの専任教員による一次審査の選考を通過したものを対象に、二次審査で各審査員が選んだアイデアに対してその審査員名を冠したアワードを授与します。
受賞アイデア
紹介
Award winners showcase
小山薫堂賞

未来さかなラボinFUKUOKA
桑原ナミ
福岡市の鮮魚市場は「産地市場」かつ「消費地市場」という全国唯一の珍しい、魚の取扱高も全国トップクラス。あまり知られていないが水産資源が豊富な地域である。また魚料理を目当ての観光客も多い。
しかし市内に観光施設が少ないのが悩みの種だ。そこで福岡市中心部にある福岡市鮮魚市場に、観光体験型施設として福岡を囲む3つの海(外海:筑前海、内湾:有明海、内海:豊前海)がもたらす魚介の恵みと、それが育む食文化・暮らし・産業を五感で体験できる“海と食”の複合ミュージアムを作り、福岡市の新たな観光資源、そして漁業関係者と消費者との交流の場を作る事で福岡、九州の水産資源の価値を高めていきたい。
審査員コメント
地元の課題解決を起点に企画されている点が素晴らしいと思いました。福岡市は日本有数の食の都として知られていますが、魚の取扱高が日本でトップクラスであるということは意外と知られていません。その豊かな水産資源を発信する海と食の複合ミュージアムを、消費地のど真ん中に位置する福岡市鮮魚市場内に設立するというアイデアはとてもリアリティがあります。
実は「EARTH MART」の最も初期の企画にも、これに似たアイデアを盛り込んでいました。かつては水産国家と呼ばれた日本も、今では漁業・養殖生産量は世界10位にも入らないほど落ち込んでいます。福岡に限らず、日本各地に五感で体感できる水産文化の拠点が誕生することは、日本の食の未来を輝かせる大きなきっかけになると信じています。
佐藤洋一郎賞

日本列島まるごと
食のミュージアム構想
内田さやか
建物を新設せず「日本を一つの巨大なミュージアム」と見立て、移動ハブを活用して食と文化の体験をネットワーク化する計画です。空港には世界の玄関口として短時間で魅力を伝えるショーケース型パビリオンを設置、主要新幹線駅には地域観光の情報やガイド施設を設置。現地の「札所」では生産者や伝統料理の現場を体験し、デジタルパスポートで学び・記録・EC購入を一気通貫化します。1施設集中型ではなく拠点を分散・連結することで、全国の観光動線を活性化し、地域経済へ直接利益を還元します。EARTH MARTの理念を継承し、巡礼文化のストーリーを軸に、弥次喜多とミャクミャクがナビゲートする日本食の未来型ガストロノミーツーリズムを提案します。
審査員コメント
いわゆる箱ものをやめて、日本列島の全体を1つのミュージアムに見立てるユニークな構想です。街ごと博物館という構想はありますが、列島全体を包み込んでしまったところがスゴイ。「巡礼」を使ったところもおもしろい。巡礼は単なる宗教活動ではなく、文化交流の場でもあったのですね。むろん、食も含めて。
願わくば、ハブ空港・新幹線駅の選択にもう一工夫欲しかった。「おいしい」「里山」など、食につながる愛称を持った空港や、「富士山」「コウノトリ」など、誰もが知っている名物を近くにもつ空港など、ガストロノミーツーリズムを前に進めるに格好の場所がまだまだあります。東海道はじめ昔の街道や宿場を使ってみるのもおもしろいかも。
石川伸一賞

FOOD CHANGER
岡本和子
新たな「食のミュージアム」として、ゲームセンターで食の未来を体験する『FOOD CHANGER』を提案する。忙しい毎日の中で、徐々に食への興味を失った体験から、食に関心が薄い人でも楽しめる「遊び」が入口となる。
舞台は、万博の壮大なビジョンとは対極の、個人的なゲーム空間だ。ゲームセンターは、日本特有の空間でもあり、全国どこにでも存在する。クレーンゲームやガチャガチャで得られるのは、食材ではなく作り手の物語や未知の食に繋がるQRコード、伝統食や特別機内食のミニチュアなどだ。予測不能な出会いが、参加者の知的好奇心を刺激する。
食べて終わりではない、一人ひとりが食の未来を「自分ごと」として描き始める、始まりのミュージアムである。
審査員コメント
食の課題の中で最も深刻なのは、「食への無関心」であると言えます。岡本和子氏の『FOOD CHANGER』は、その見えにくい課題に対し、遊びを通じて新たな関心を喚起しようとする意欲的な提案です。クレーンゲームやガチャガチャといった日常的な仕掛けを入り口とし、偶然の出会いを通じて生産者の物語や伝統食、未来の食文化へと人々を誘う点に独自性があります。そこから得られるものは単なる景品ではなく、作り手を応援する気持ちや土地への愛着であり、子どもから大人、さらには海外の方にとっても強い共感を生み出すでしょう。楽しみながら自然に食を「自分ごと」として考える契機を提供する取り組みとして高く評価でき、食の裾野を広げ、担い手の励みとなる可能性を秘めたアイデアであると考えます。
大屋洋子賞

海・山・里山をまるごと実体験する
「Earth Farm」
岩瀬友理
スーパーで食べ物を買い、旬の食べ物さえ知らず、どんなふうに育つか、誰が収穫しているのかも知らずに生きている私は、EARTH MARTであらためていただいている命の大切さを感じた。命を大切にするためには、それを実感できる場所が必要だと考える。
Earth Farmは一年を通して春夏秋冬の生産の現場を体験できる場所である。子供向け、観光客向け、プロ向けのプログラムがあり、海、山、里山の土地を活かし、漁業、山菜採り、農作物の収穫を季節に合わせて体験できる。また、発酵などの伝統的な食文化の体験や、録食などの未来の食体験もできる。大きなキッチンラボがあり、国内外からシェフや研究者を招いてフォーラムも可能である。
審査員コメント
海、里山、山に恵まれた具体的なエリアを候補地とし、その地域ならではの食体験に加えて、過去から未来の食までを学べる凝縮された体験型ミュージアムのアイデアで、見ていてとてもワクワクしました。提出された動画の構成・デザインも秀逸です。
スーパーマーケットをモチーフとした大阪・関西万博「EARTH MART」での“食を通して、いのちを考える”経験から、より体験型で生産現場に近いEarth Farmへという流れもしっくりきました。
産学連携など幅広いステークホルダーを巻きこみ、食の社会課題解決からコミュニティ形成までを担うラボ機能も兼ね備えていることで、エリア外からの来訪を誘引するだけでなく、地域活性化にも繋がり在住者にとっても有意義な拠点となりそうです。
ディスカッション
プログラム
Discussion program
アワード受賞者と審査員による
ディスカッションプログラムを実施します。
アイデアの授賞理由とそのアイデアの
さらなる発展の可能性について
ディスカッションを行います。
日時
2025年10月1日(水)11:00-12:30(予定)
場所
都内会場(対面)・オンライン ハイブリッド開催
これまでの万博特別講義
2025.01.10
小山薫堂先生による万博特別講義
登壇者:小山薫堂
大阪・関西万博で小山先生がプロデュースをする「EARTH MART」という食をテーマとしたパビリオンの構想についてや、「食を通して、いのちを考える。」というテーマについてお話しいただきました。「食事は他の命をいただく行為」という観点から、「いただきます」という言葉に込められた感謝の重みを深く考える時間となりました。
2025.04.18
食を通して、いのちについて考える
登壇者:佐藤洋一郎、奥津爾(オーガニックベース代表/オーガック直売所タネト店主)
ファシリテーター:大屋洋子
「EARTH MART」内の「野菜のいのち」の展示について、100年で激減した地域在来種の多様性と文化的価値を議論しました。種の保存を起点に、地域の文化や祭り、食文化と一体で継承する意義を訴え、農家・料理人・消費者の連携が不可欠。若手料理人や消費者の関心が高まる中、種の学校や生産・料理人ネットワーク、地域直売所での普及活動など具体的取り組みが進行中とのこと。こうした活動が日本の食文化の持続可能性と多様性を支え、世界への発信の鍵になるとお話しいただきました。
2025.04.29
日本の食の知恵から、未来について考える
登壇者:外村仁(京都芸術大学 客員教授 食文化デザインコース「フードビジネス構築」講義担当、Food Techエバンジェリスト/投資家)、村田吉弘(和食料亭「菊乃井」三代目主人)
ファシリテーター:大屋洋子
「EARTH MART」内の「EARTH FOODS」の展示について、日本の食の未来の展望についてお話しいただきました。海藻を持続可能なタンパク質源と捉え、その世界的活用の拡大を提唱しました。麹、日本酒、味噌、醤油など発酵食品の独自性や、大根・米・大豆の多彩な利用にも触れ、わさびやみりん、日本酒などの海外人気を背景に、日本料理の発信力強化と英語情報での発信の重要性、発酵文化を軸にした国際交流・理解促進が大事であるということをお話しいただきました。
2025.05.20
未来について考える(フードテックから考える)
登壇者:石川伸一、古川英光(山形大学教授/ソフト&ウェットマター工学研究室代表)、野元知子(ソニーグループ株式会社 食プロジェクトリーダー/味わう株式会社 代表取締役)
ファシリテーター:大屋洋子
「EARTH MART」内の「進化する冷凍食」の展示について、古川先生からは−196℃の凍結粉砕技術で食材を保存したり、未利用資源を活用する可能性についてお話しいただきました。野元さんからは味を再現するテクノロジーについてお話しいただきました。石川先生からも思い出の料理の再現やAIとの協働による創造性、産業化への期待が寄せられ、テクノロジーが食の未来を切り拓く可能性が強調されました。未利用の食資源を高度技術で有効活用できること、調理技術や味わいをデータ化して継承・再現することで食文化の幅が広がること、そしてAIと人間の協働が新たなクリエイティビティと産業創出を促す可能性についてお話しいただきました。
2025.05.21
「EARTH MART」グループ見学(2025年5月21日、5月31日、6月15日 計3回実施)
教員引率の元、「EARTH MART」を見学し、見学後ディスカッションを行いました。